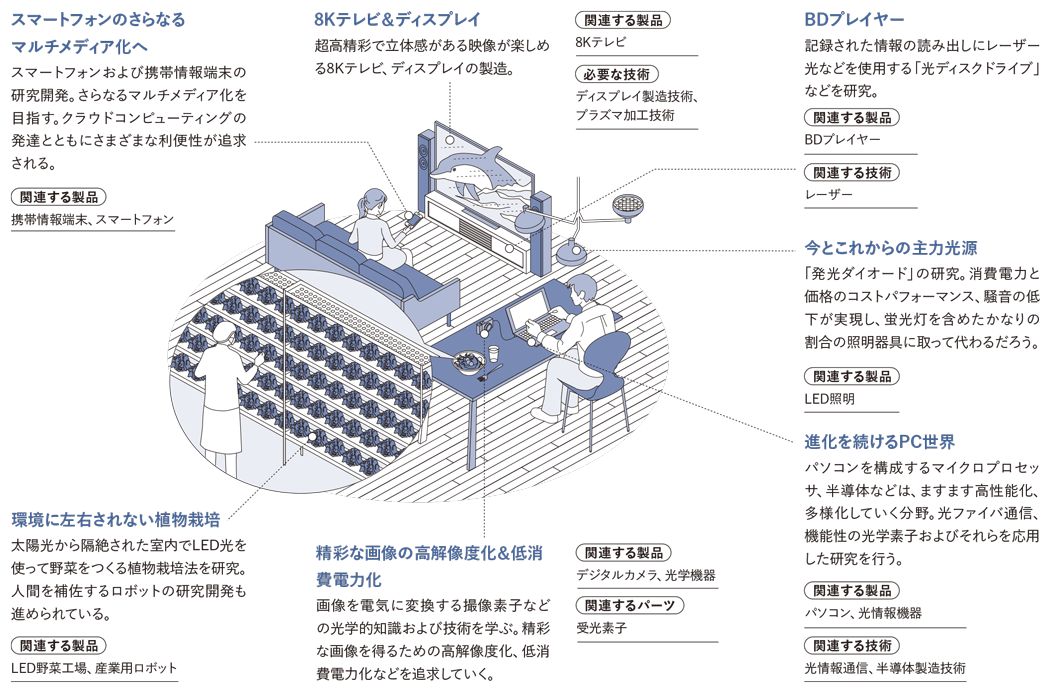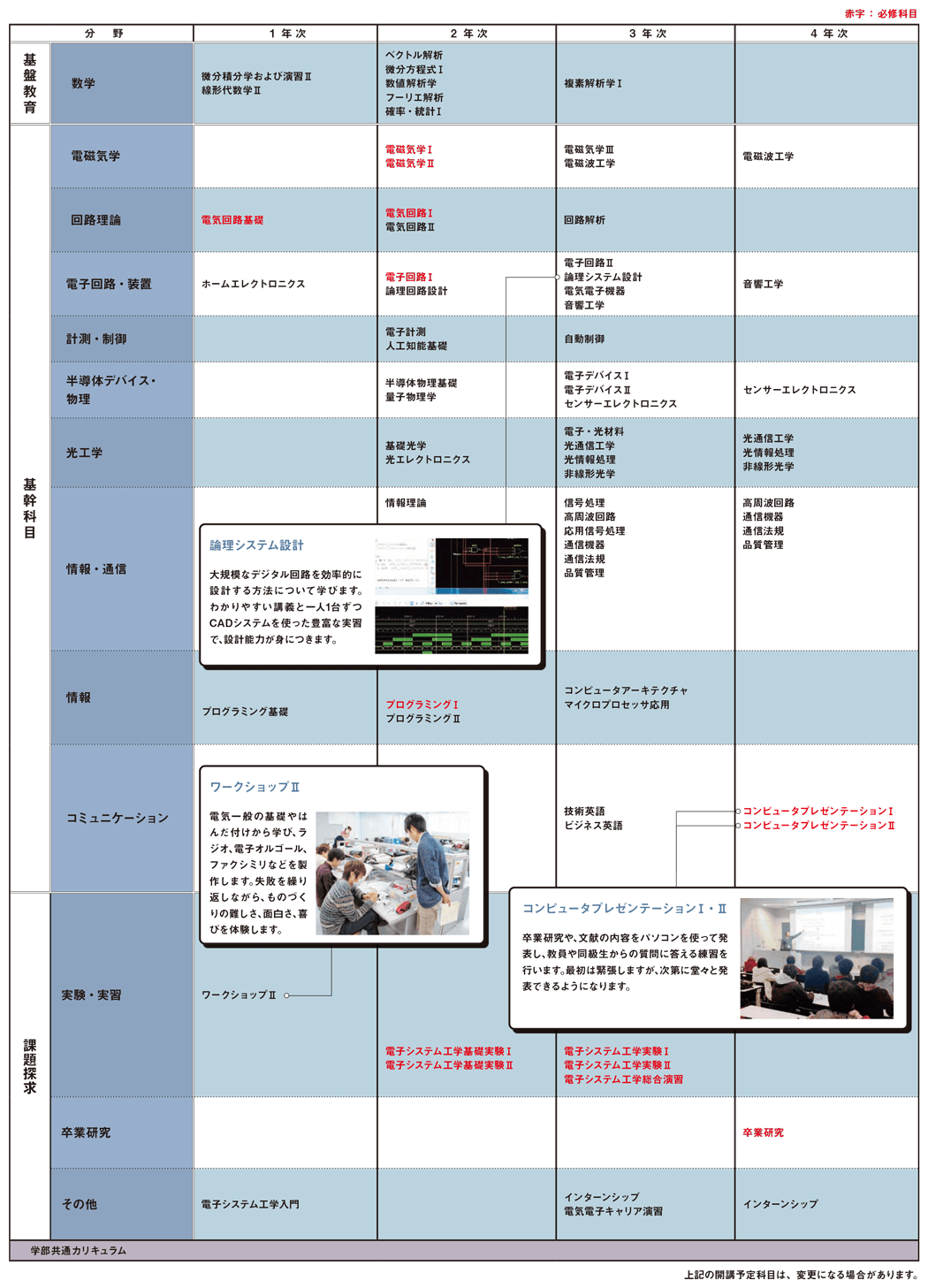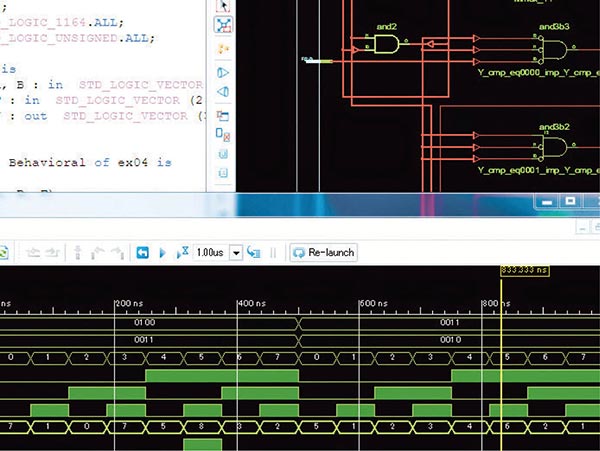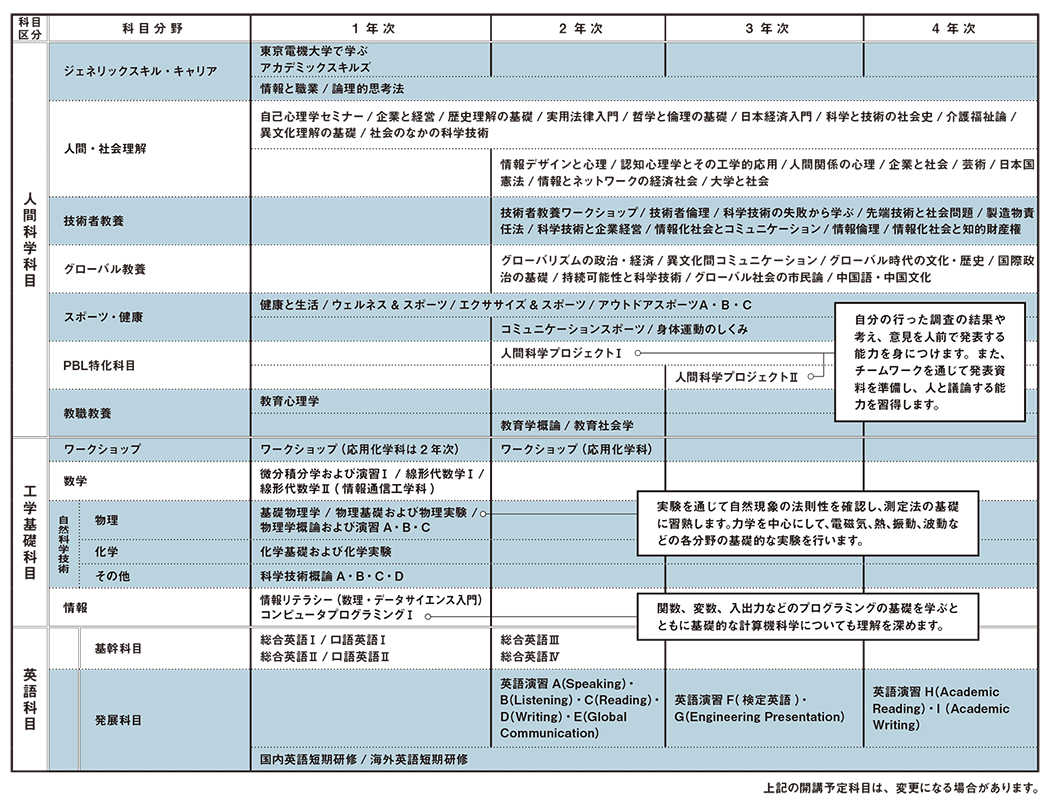工学部 電子システム工学科 学科オリジナルサイト

スマートフォン、パソコン、LED照明など、身近な製品の基礎となる電子・光・情報に関する技術を身につけた、社会に貢献できる人材の育成を目的とします。
製品を企画立案し、開発のリーダーとして活躍できるように、基礎から応用までの幅広い知識・技術に加え、調査能力や国際感覚なども養成します。

3つの特長
-
電磁気学、電子回路、プログラミングなどの基礎を重視
電子システム工学技術は極めて進歩が速い技術分野のため、基礎を低学年次で身につけることが肝要です。本学科では電磁気学、電気回路、電子回路、プログラミングなどの基本科目の内容を豊富な演習を交え、確実に習得できます。また理論だけでなく、実験やワークショップを通じて興味を育てます。
-
電子システムの広範な技術を学ぶ
電子システムに関する技術は極めて範囲の広い技術分野です。実社会で即戦力になれるよう、さまざまな技術の概要を学びます。将来、どんな製品が必要になるかを考え、新製品を企画立案し、開発プロジェクトのリーダーとして活躍するためにも、広範囲にわたる技術の全体像を把握しておくことが不可欠です。
-
グローバルに活躍するための英語力、プレゼンテーションスキルを培う
社会では学力・技術が秀でていても一人でできる仕事はほとんどなく、日本だけでなく海外の技術者とも円滑な意思の疎通が必要です。そのためのプレゼンテーションスキル、ビジネス英語などを学びます。また、インターンシップや卒業研究を通じてグループワークを体験的に学び、就業力の向上につなげます。
電子システム工学科の学び
-
家庭用電子機器
スマートフォンなど身の回りの高度な家電製品の原理を学び、製品の企画・開発に携わる人材を育成します。
-
高機能材料・光デバイス
高性能な材料や新機能デバイスの開発技術を学び、新たな産業の種を開拓できる人材を育成します。
-
電子情報・光通信システム
さまざまな情報機器をつなぐ高度情報通信システムについて学び、IT技術に貢献できる人材を育成します。
-
生産・制御技術
さまざまな製品を実際に生産するための技術を学び、製造工程の設計・管理に携わる人材を育成します。
できる、つくれる、こんなこと!
卒業後の就業者の業種別割合(2023年度卒業者実績)
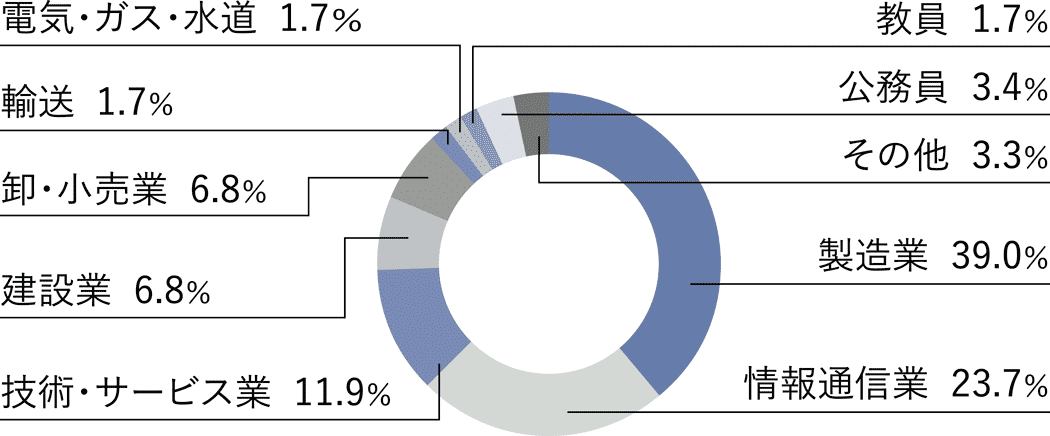
[卒業者数]
74名
男子:69名/女子:5名
主な就職実績
ソニー / 日立製作所 / NEC / 富士通 / ソフトバンク / 東芝 / JR東日本 / 三菱電機 / キヤノン / NTTデータ / パイオニア / 大成建設 / 京セラ / JR東海 / 本田技研工業 / いすゞ自動車 / 日立システムズ / ボッシュ / 日本精機 / 高砂熱学工業 / 関電工 / NECソリューションイノベータ / 日本サムスン / 岩崎通信機 / セガ など
大学院進学
10名 (2023年度卒業者実績)
男子:9名
女子:1名
進学率:13.5%
目指せる資格
第一級陸上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、陸上無線技術士(第一級・第二級)、電気通信主任技術者、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、建築施工管理技士(1級・2級)、建築設備士、建設機械施工管理技士(1級・2級)、技術士・技術士補、公害防止主任管理者、消防設備士(甲種)、弁理士 など
関連コンテンツ
その他のコンテンツ
- 大学紹介
- 基本情報
- 学長挨拶
- 顧問学長対談
- 副学長・学部長等 役職者
- 建学の精神と教育・研究理念
- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー
- 大学のあゆみ
- 大学の取り組み
- 情報公開
- 認証評価、自己点検・評価
- ホームカミングデー
- 東京電機大学が求める教員像
- 教育関係附置施設
- キャンパス紹介
- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー
- 学園紹介
- 学校法人東京電機大学概要
- 理事長挨拶
- 理事・監事
- 評議員
- 事業・財務情報
- ガバナンス
- 学園創立100周年宣言
- 学園広報物
- TDUコメンテーター教員紹介
- 学園へのご寄付
- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像
- 学園創立110周年記念事業
- 系列校・関連機関
- 寄附行為等
- 危機管理
- 新型コロナウイルス感染者状況
- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~
- 学部
- システムデザイン工学部
- 未来科学部
- 工学部
- 工学部第二部
- 理工学部
- 大学院
- 大学院での学び
- 先端科学技術研究科
- システムデザイン工学研究科
- 未来科学研究科
- 工学研究科
- 理工学研究科
- 入試・オープンキャンパス
- 大学入試
- 大学院入試
- インターネット出願/マイページ
- 入学者選抜要項
- 入試結果
- オープンキャンパス2025
- オンライン個別相談会
- 進学相談会
- キャンパス見学会
- キャンパス自由見学
- キャンパス見学
- メールマガジン
- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと
- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)
- 1分で電大が分かる!ショート動画
- 受験生への応援メッセージ
- キャリアプログラム
- 学内就職サイト
- 就職支援
- 資格取得・教員免許
- 公開講座
- 履修証明プログラム
- 実践知教育
- 留学・国際交流
- 本学へ留学希望の方
- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)
- 海外に留学希望の方
- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)
- 海外留学動画(学内者専用)
- 国際センター
- TDU International Workshop
- International Workshop
- スチューデントアンバサダー
- 国内でできる国際交流
- 在留期間更新許可申請
- 学生生活
- 学生要覧
- 履修の手引き
- 教職課程
- シラバス・時間割
- 年間予定
- 学習サポートセンター
- 学生アドバイザー
- 障害のある学生への支援
- その他授業関係
- 学費
- 奨学金
- 教育ローン・短期貸与金制度
- 保険制度・経費補助
- 証明書発行・事務窓口
- 学生相談室・健康相談室
- 休学・退学などについて
- クラブ・サークル活動
- 学生食堂と売店
- 車両通学
- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について
- 東京電機大学後援会
- 教育訓練給付制度