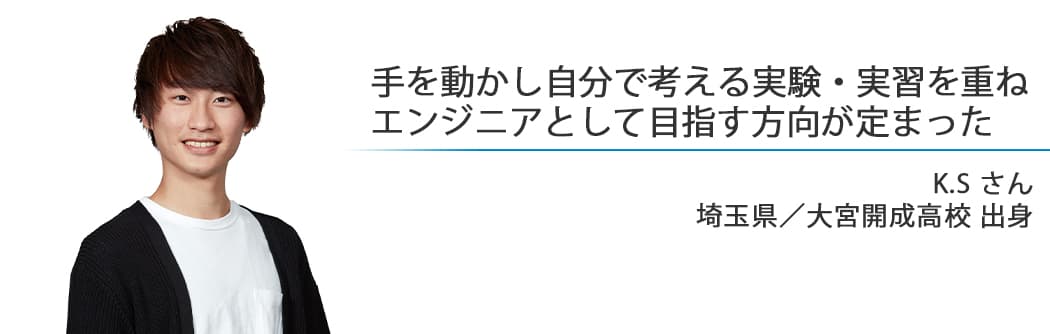将来は通信系の仕事に携わりたいと思っていました。通信分野に重きを置きつつ、プログラミングなどの必須知識も学べることで、将来の可能性が広がると思い、本学科を選択しました。
難しさと面白さを実感した、初めてのものづくり
初めてものづくりを体験した「ワークショップ」。初回の授業でLANケーブルをつくりましたが、配線に苦労しました。回路の製作では設計図に合わせて部品を選び、回路を組みます。はんだ付け以外はほぼ初めての体験で、ダイオードを逆に取り付けて壊してしまうなど、失敗を繰り返しながらも何とか完成。高校時代に習った物理の知識を生かしながら、正しい電流と電圧の値が取れた際には達成感があり、ものづくりの面白さを実感しました。
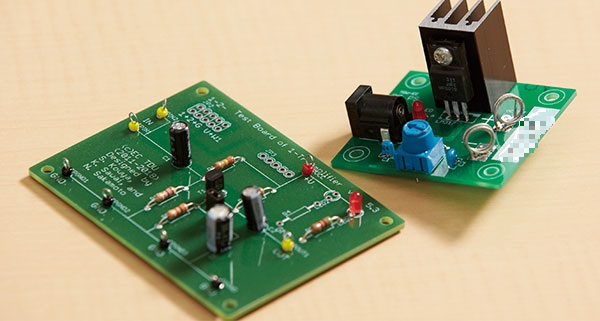 実習でつくった回路。小さな回路は実験用の電源装置。
実習でつくった回路。小さな回路は実験用の電源装置。
「なぜ?」を自ら突き詰めてプログラミングの知識を習得
プログラミングの授業では1年次にC言語を学び、2年次には「データ構造とアルゴリズムⅠ」でJavaを用いて、毎回違う課題に挑みました。自分でコードを組み、エラーコードが出たら「なぜ?」を教科書で確認したり、友人のサポートで解決しながら知識を蓄え、最後には100行を超えるプログラムを書ける力がつきました。トライアルアンドエラーを繰り返し、「なぜ?」を突き詰めて解決するプロセスは、別の言語を学ぶ際にも役立ちました。
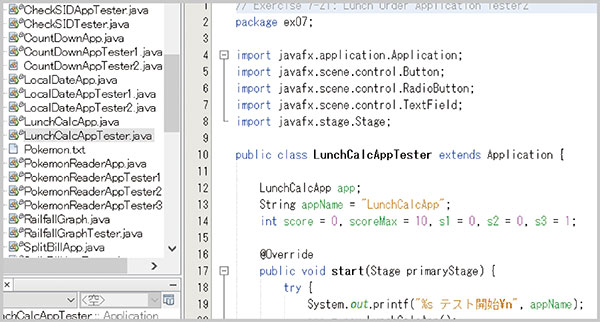 Javaで作成したプログラミングのソースコード。
Javaで作成したプログラミングのソースコード。
何度もレポートを書き直して培った考察力
1・2年次に学んだ基礎知識を応用し、専門性の高い実験に取り組む「情報通信工学実験」。座学で学んだ知識を実験で実証しますが、難易度が高いため予習は不可欠です。隔週で行われる実験後にはレポートを作成。実験結果に対し「なぜそうなったか」を考察し自分の答えを出しますが、先生から再提出を求められることも多々あります。考える視点を変え、何度も書き直すのは苦労しましたが、そこで培った考察力は、卒業研究でも生かされています。
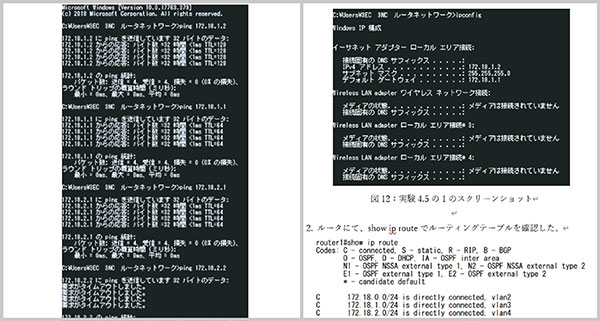 何度も書き直した「ルータネットワーク構築」のレポート。
何度も書き直した「ルータネットワーク構築」のレポート。
4年間の集大成で「世の中にないもの」をつくる
「情報通信プロジェクト」では、複数のテーマの中から“マイコン”を選択。4人1組の班で、Arduino(アルデュイーノ)を使い、課題である“世の中にない面白いもの”の製作を行いました。私たちは、高度難聴者用の補聴器を製作。車のクラクションなどの危険な音を、首にかけた機器の振動で知らせる仕組みです。ハードウェアとソフトウェアの開発には、これまで培った知識と技術が生かされており、積み重ねて学ぶ大切さを実感しました。
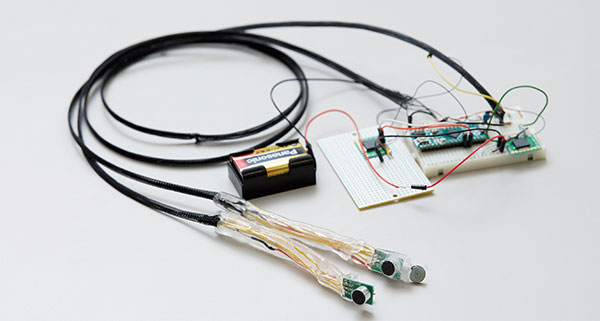 製作中の「高度難聴者用の補聴器」では、ハードウェア開発を担当。
製作中の「高度難聴者用の補聴器」では、ハードウェア開発を担当。
日本電気株式会社(NEC)
内定先では、システムエンジニアとして、社会基盤となるシステム開発担当者の一員として働く予定です。働き方改革や労働力不足が課題となる中で、AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)といった最新技術を用いて、社会をより豊かにするシステムの開発に携わり、人々を幸せにしたいというのが私の夢です。
プロ野球をスタジアムで観戦!
好きなチームを応援するために、シーズン中は10回ほどスタジアムに足を運んで観戦しています。テレビ中継もほぼ全試合を見ていますが、スタンドで応援したくてウズウズしています。

関連コンテンツ
その他のコンテンツ
- 大学紹介
- 基本情報
- 学長挨拶
- 顧問学長対談
- 副学長・学部長等 役職者
- 建学の精神と教育・研究理念
- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー
- 大学のあゆみ
- 大学の取り組み
- 情報公開
- 認証評価、自己点検・評価
- ホームカミングデー
- 東京電機大学が求める教員像
- 教育関係附置施設
- キャンパス紹介
- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー
- 学園紹介
- 学校法人東京電機大学概要
- 理事長挨拶
- 理事・監事
- 評議員
- 事業・財務情報
- ガバナンス
- 学園創立100周年宣言
- 学園広報物
- TDUコメンテーター教員紹介
- 学園へのご寄付
- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像
- 学園創立110周年記念事業
- 系列校・関連機関
- 寄附行為等
- 危機管理
- 新型コロナウイルス感染者状況
- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~
- 学部
- システムデザイン工学部
- 未来科学部
- 工学部
- 工学部第二部
- 理工学部
- 大学院
- 大学院での学び
- 先端科学技術研究科
- システムデザイン工学研究科
- 未来科学研究科
- 工学研究科
- 理工学研究科
- 入試・オープンキャンパス
- 大学入試
- 大学院入試
- インターネット出願/マイページ
- 入学者選抜要項
- 入試結果
- オープンキャンパス2025
- オンライン個別相談会
- 進学相談会
- キャンパス見学会
- キャンパス自由見学
- キャンパス見学
- メールマガジン
- 大学案内
- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと
- 受験生向けSNS一覧
- 1分で電大が分かる!ショート動画
- 受験生への応援メッセージ
- キャリアプログラム
- 学内就職サイト
- 就職支援
- 資格取得・教員免許
- 公開講座
- 履修証明プログラム
- 実践知教育
- 留学・国際交流
- 本学へ留学希望の方
- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)
- 海外に留学希望の方
- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)
- 海外留学動画(学内者専用)
- 国際センター
- TDU International Workshop
- International Workshop
- スチューデントアンバサダー
- 国内でできる国際交流
- 在留期間更新許可申請
- 学生生活
- 学生要覧
- 履修の手引き
- 教職課程
- シラバス・時間割
- 年間予定
- 学習サポートセンター
- 学生アドバイザー
- 障害のある学生への支援
- その他授業関係
- 学費
- 奨学金
- 教育ローン・短期貸与金制度
- 保険制度・経費補助
- 証明書発行・事務窓口
- 学生相談室・健康相談室
- 休学・退学などについて
- クラブ・サークル活動
- 学生食堂と売店
- 車両通学
- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について
- 東京電機大学後援会
- 教育訓練給付制度