FD/SDセミナーレポート「英語による教授法 -本学の専門教育における実践事例-」
2017.10.10
教育改善推進室主催、平成28年度FD/SDセミナーは<英語による教授法-本学の専門教育における実践事例->と題して、本学教員3名による英語を使用した授業の実践事例の紹介とディスカッションを行いました。本学のグローバル化促進を目的としたFD/SDセミナーは本年で3年連続開催となります。
(2016年6月21日に開催した内容を編集したものです)
グローバル生産技術を目指して

東京電機大学
工学部 機械工学科
松村 隆 先生
私の専門である「生産技術」の分野では、日本の製造業は生産拠点を海外に移しています。グローバル化なくして、日本の「ものづくり」はありえません。海外に生産拠点を置く以上、現地の方と英語でコミュニケーションをとる必要があります。米ボーイング社と共同研究もしているため、研究室では英語を使っています。年に1回は同社社員が来訪して、学生も接する機会があります。また、卒業後の本学学生は、フットワーク軽く様々な場所で活躍する人材も多いと思っています。
そのような背景もあり、綺麗な英語ではなく、業務上使用する「伝達手段としての英語(専門用語)」を身につけてもらうことが重要です。技術を伝えるための英語は、専門用語さえ知っておけば難解なビジネス英語よりはるかに易しいものです。専門用語・テクニカル単語さえ知っていれば、比較的早い段階で、英語で実務的なコミュニケーションが取れるようになります。
しかし、生産技術分野の専門用語を教えてくれる英会話教室はありません。そこで大学の講義で、「日本語と同時に、英語で専門用語の知識を得られる」機会を与えようと考えたのが、今からご紹介する私が実践している授業です。
「専門用語も分からない学生に、英語で講義したら、何もわからない状況になるのでは?」
という事を危惧する気持ちもあるでしょう。確かにその可能性も否定できません。
また、授業運営の面で、「授業で資料を配布したら、学生が安心して寝てしまう・内職してしまう・途中退室してしまう」といったこともあるかもしれません。
こうしたことを考慮して、私が実践しているのが「日本語表記のない『英語のみの配布資料』を配り、講義はその資料を用いて『日本語』で行う」という方法です。
生産技術のライバルであるドイツでは、技術流失を防ぐためにドイツ語で会話しているといいますから、日本も技術流出を防ぐことや文化・技術の継承の面では日本語で行う方が良い面もあるかもしれませんが、グローバル社会においてはやはり英語も必要です。
授業でプロジェクターが2画面ある教室を利用する際は、一方に配付した英語表記を映し、もう一方は和訳をした資料を投影します。学生の手元には英語表記の資料しかありませんので、授業の時間に必死に日本語のメモを取り始めます。講義は日本語で専門用語を解説することから始めますが、配布資料には絵・図しか描かれておりませんので、深く理解することは難しくなります。細部の説明を理解するために、教科書を指定しその部分を読んで復習するよう促します。日本語のみしか使わないと、日本語での専門分野の知識しか身につきませんが、この方法であれば、講義内容に関して日本語・英語双方の知識を同時に身につけることが出来ます。私の受け持つ授業では、このスタイルを主としています。
資料作成の際に大切な点は、意図して不完全(空白のある)な資料を作成することです。講義を聞いた上で、学生自ら書き込みをして完成させるような資料にして、理解を促しています。資料上の英語の文章表現は、簡単なものであることも重要です。講義はあくまでも専門科目であって、英語の授業ではありません。単語を繋げていくようなレベルで十分です。更にこの資料を効果的に使ってもらうために、テストでは配付資料のみを持ち込み可にしています。資料を不完全なままにしておくと、テストの際にこの資料を持ち込んでも何の役にも立ちませんので、学生は授業を必死に聞いてくれるようになります。聞きながら書き加えていくことで、学生の理解度や達成感も高まる効果が得られているようです。「単位を修得したら捨てられてしまう資料ではなく、学生自身が書き加えた資料が学生の将来の技術英語の辞書」として活用されることを願っています。
海外協定校での出張講義

東京電機大学
理工学部 電子・機械工学系
大西 謙吾 先生
アメリカの私立大学では、週に2-3回同じ講義がありますが、必ず予習として教科書30ページ分くらいのリーディングが課され、復習として演習問題2-3題に取り組みます。アメリカの大学では予習を前提に授業を進めており、基本知識を持っていることが前提ですので、予習・復習しない学生は授業についてこられません。授業は例題の解説が主であり、学生は確認するために質問をします。このような授業スタイルがよいと思ったのですが、日本での実践はやや難しく、実践する場を探していたところ、協定校での特別講義の機会が得られました。
本学海外協定校の1つであるフランス国立高等精密機械工学大学院大学(ENSMM)での出張講義のお話をしたいと思います。ENSMMは精密機械を専門にしている大学院大学です。フランス語圏ですので、英語が母国語では無いという点では本学と同じです。日本との違いは、黒板消しがない点です。スポンジに水をつけて黒板を消すのですが、とても効率が悪いので2年目以降はスライド資料を造りました。
私の科目は応用系であり、工学をリハビリの中にどう利用するか、デバイス設計に品質工学をどのように適用するかなどが専門です。ENSMMでの授業は2日間で合計8時間の授業と2時間の試験を担当しました。ENSMMからは、日本で行っている専門科目を英語で講義して欲しいと要望されました。初日はリハビリテーションロボットの技術紹介と研究事例の紹介をし、2日目はパラメーター設計の解説を行い、演習で自転車ブレーキの基本機能が何かを考えてもらうことで、どのような設計、実験が必要かを考えてもらい、受講者と対話形式で議論・解説を行いました。ENSMMの学生には授業を行う前日に30ページほどの配付資料を先に読んでもらい、内容がわかるように英語での講義もゆっくりと話すようにしました。投影スライドも長文の英語が書いてあると、母国語でない学生が読むのも大変で、理解が難しくなります。そのため、できるだけ単語だけで分かるように写真等を多用し、英語の数式は色分けのスライドを作り、わかりやすく作成しました。配付資料は空欄のあるものにし、学生が講義を聞きながら自身で埋めて完成するものを作成しました。
試験については、海外の学生は癖のある字を書く人が多いので、記述が多いと採点する側も読むのが大変になります。そのため、正誤問題や穴埋め問題を中心に採点しやすいものを心がけました。問題文も教科書と同じような表現を用い、学生が一度でも読んだことがあれば何となくわかるような文章にしました。試験では配付資料の持ち込みを可にしていますので、学生自身で書込みをした資料があればすぐに解けるように配慮して特別講義の締めと致しました。
多国籍な学生を対象とした授業づくり
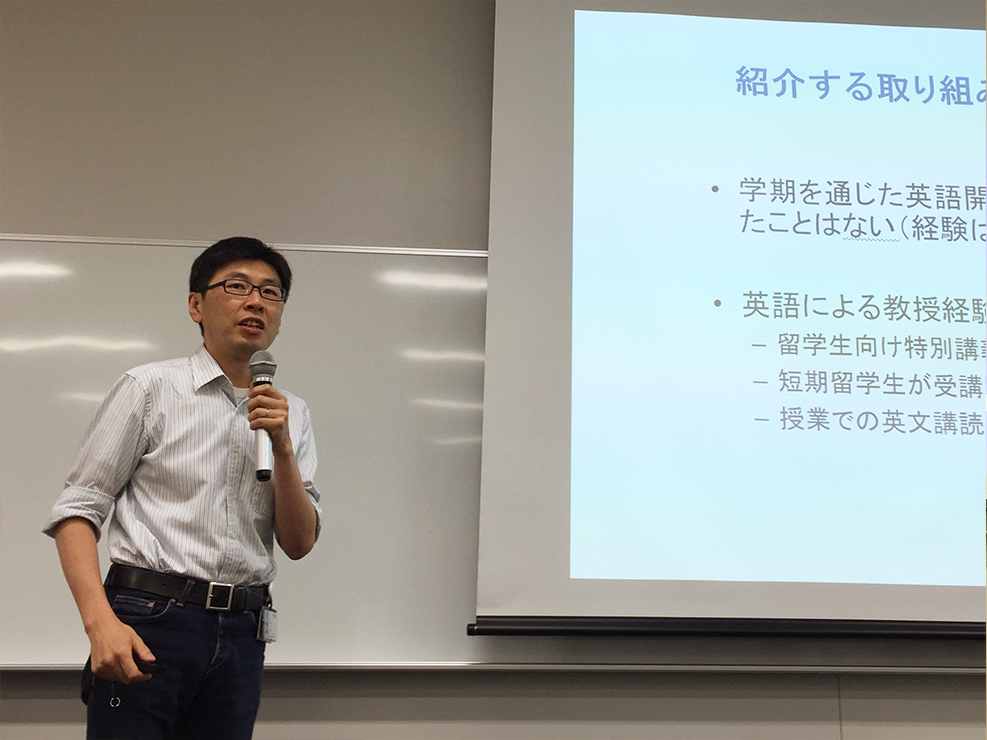
東京電機大学
情報環境学部 情報環境学科
伊藤 俊介 先生
私は建築計画が専門であり、建物をどのように設計するかを研究しています。技術的なことは殆どなく数式は使いません。問題を解くよりは考え方を理解させる、あるいは建築計画のデザインや手法を知るような、理系ではあるものの教養寄りの科目も担当しています。
英語で授業を行うことについて「英語での授業では、知識・情報の伝達量が減少する」「日本語での授業でも理解が十分ではない」といった意見をよく聞きます。
グローバル化・国際化に振り回されるべきではないという意見もあります。
しかし、学生が大学で新しい専門の勉強をすることはそもそも新しい学問であるから、それを始めから外国語でやってもデメリットは無いのではないかという想いがあります。
情報環境学部には、短期留学生も多くいるのですが、まず留学生対象講義のご紹介をします。建築の授業は写真やイラストを使用したビジュアルな資料が多くなり、英語の説明でも理解がしやすい面はあります。
日本人学生に対して英語で授業を行っても、同様にビジュアルな資料をみることで、理解は深まります。これは建築分野の特性ではあります。
台湾やフィリピンからの留学生と日本人学生向けに行った特別講義の際には、学生から資料に日本語と英語の両方表記をして欲しいという要望があり、イラストにテキストを入れてわかりやすくしました。手間がかかることもあり、普段はこのようなことはしないのですが、作成して感じたことは、学生の理解が深まるということと日本人学生にとっても専門用語の英語表現などが分かるというメリットがあることでした。
私の担当する専門の講義を、日本語を話せる短期留学生が一学期間履修したことがありました。この時には、配布資料は英語と日本語の両方を表記しました。留学生にとって日本語の漢字は「読み」が難しいので、全てルビをふりました。講義は日本語でややゆっくり行い、複雑な部分に関しては英語の補足をしながら授業を進めました。これは英語で授業を行う先生と真逆のパターンだと思って頂ければ分かりやすいと思います。
この授業を行って感じたことは、「重要な情報の伝達量は減っていない」ということです。事例紹介など、割愛した部分もありましたが科目の骨格部分は減らしていません。この方法は日本人学生にとってもメリットがあり、専門用語を英語で知ることができる。そして英語で補足している分、説明を二度聞くことができます。
もう1つ、これも英語での教授法というよりは、多国籍な受講生がいる環境で、どのように運営したかという点についてのご紹介です。
レポートで、学生自身の生まれ育った環境や場所の過去・現在の航空写真を用いて、都市開発などでどんな構造的な変化が起きたか分析するという課題を出しました。留学生のおかげで、様々な国の事例を知ることが出来て、学生たちもとても参考になったそうです。建築という学問は文化的な背景が非常に重要な学問であり、日本人同士であればその背景説明を省いても共有可能な場合があります。しかし、海外の方がいれば、文化の前提や歴史・概念などを英語で説明する必要があり、これはとても難しいものです。
例えば、「気配」「にぎわい」「ふれあい」などは日本語での会話では聞き流せますが、英語で説明するとなるときちんと概念を説明する必要があります。外国の方と話す際にきちんと説明しないと「気配とはなんだ?」と聞かれることになります。
英語で説明する機会があることで、何気なく使っている日本語の意味を日本人学生もしっかりと理解が出来るようになり、用語の概念やことばや事項の関連性、意味構造などをきちんと理解できるようになります。これは、外国の学生が混在する大きなメリットの一つです。
別の年度の大学院の授業では、翻訳されていない論文を取り上げる必要があり、そのまま配付して資料としました。日本語では流し読みして理解できる内容でも、英語ではしっかりと読む必要があり、これによって上辺だけでない深い理解に繋がるようになり、ディスカッションも活発になったというメリットもありました。
余談ではありますが、海外の大学で授業を聴講した際、日本とはかなり異なり、大学院生向けの講義であっても基本や理論を大切にしている印象を受けました。これは分野によって異なるのかもしれませんが、事例紹介などよりも理論の背景などに重心を置いていたように感じます。
様々な経験から感じた点として、英語で授業を行っても基本的な情報量が減少することはなく、授業の肝心な部分は伝わるものだと思います。学生の将来を考えると、英語での授業はメリットがあり、特に大学院では英語で授業を行ってもいいのではないかと思っています。
パネルディスカッション

パネルディスカッションでは、国際センター長の小林岳彦先生がコーディネーターとなって様々な議論を行いました。
英語の資料作成にどのくらい時間や手間をかけているのでしょうか?
【松村】私の場合、2週間程度です。日本語で作成済みの資料がベースであり、さほど英語版作成に時間はかかりません。
【大西】私も日本語で作成済みのものを英語にしているので、さほど時間はかかりません。資料自体もあまり文章をいれないように作っています。他には、授業でどのように英語で説明するかを考える時間がある程度は必要です。
【伊藤】もともと資料に沢山の文章を記載しない上、日本語で作成済みの資料を英訳しているだけなので時間はかかりません。日本語の資料を作成する1.5倍くらいの時間ではないかと思います。
他には英語で講義をする際に、英単語がパッと出てこない瞬間はあるので、自分用に使う英単語メモは準備しています。
受講者には英語力に開きがあるかと思います。学生個々人の英語力の差をどのように考慮しているのでしょうか?
【松村】資料を英語で書いているだけで、内容そのものは教科書に日本語で書かれています。「教科書のこのページを良く読みなさい」と伝えていますので、特に英語力の差は意識しません。私の科目の場合、英語力を磨くというよりは、海外で仕事したときに「この単語は見たことがあるな」とか「あの科目でやったな」と抵抗なく受け入れてもらえるかどうかを重視しています。そのため英語力の差はあまり問題が無いように思います。
【大西】学生が基本的な内容を理解していないと、授業に出ても教員が英語で何を話しているのかわかりません。英語(単語や表現など)をきちんと見せれば、さほど困ることは無いかと思います。見せることで、「目に入ってきた情報」と「耳で入ってきた情報」が繋がるので良いと思います。フランスの学生も母国語は英語ではないので、英語ができる学生はすごくできますが、不得手な学生は全然できませんので、日本でもフランスでも状況は同じと言えば同じです。フランスの学生に対しても話すペースはゆっくりで、できるだけ単語レベルで理解できるように言葉を並べるのが大切だと思います。
【伊藤】正直に言えば、英語の長い文章に対する学生の読解力はかなり不安があります。学生に課している文献講読でも、課題は訳文に高いレベルを求めていないと説明した上で中身を読み解くように伝えています。翻訳されていない文献を使った際は、学生と一緒にその中身を読み解くようにしたところ、学生の理解も深まりました。
英語で授業や発想を行うことと、日本語で授業や発想を行うことに何か違いを感じることはありますか。
【大西】スピードの違いは感じませんが、イメージを伝えようとすると文化的な背景を知っていないとイメージが伝わらない。その点では、フランスで授業をした際は文化的な背景を知らない事項が多いので、「たとえ話(比喩)」が使いづらいため、イメージを伝えるのが難しいということがありました。比喩を考えても、日本的な発想の比喩しか出てこなかったのです。「これで伝わるかな」と悩みながら授業をやっていた面はあります。日本で、英語で授業を行うとしたら、日本的なイメージのものを単純に英語で訳しながら伝えることはできます。でも日本で、アメリカのポップカルチャーを知らない人に対して、それを例え話にしても誰にも伝わりません。そういう文化的背景は少し意識して考えないといけないと思います。
【松村】私もENSMMで出張講義をしましたが、日本とは異なる講義をしました。短期の集中講義ですので、基礎知識を長く教えるような講義ではなく、ENSMMという大学の性質を踏まえた講義をしました。やはり問題は学生の文化にあると感じます。10年以上、ENSMMで講義をしていますので、彼らの嗜好が何となく分かってはいます。フランスは理論的とか数式とか、そういう部分を伝えると喜んでくれます。ENSMMの学生は、あまり英語を理解している学生はいないように感じます。授業が理解できなくなってくると、学生達の私語が多くなってきます。その点では、日本の学生の方が授業態度に関してはいい面もあります。
英語での教授法は、学年は何年くらいからが実施しやすいか。
【松村】私の場合、3年次の専門科目です。私の授業手法は、「授業のやり方」であるだけであって、どの学年から実施した方が良いというのは無いと思います。授業は日本語で行っていますので、通常の授業内容がわかれば、どの学年からでも理解できるものだと思います。
【大西】先生と同じ考えです。数式などが読めないと、そもそも何を言っているのか分かりません。基本的な事項を理解していれば、何年生から始めても大丈夫だと思います。私の考えは学部生よりは、大学院生に重点的に行う方が良いかなと思っています。
【伊藤】私も同じ考えです。学年は特に問わないと思います。学部生の場合、専門知識がある上級生の方が英語で授業をしても理解も早いと思います。その意味でも、効果が大きいのは上級学年だと思います。ただ、下級生向けに「やらない方が良い」ということではありません。
ALで英語を取り入れるのはどうでしょうか
【松村】私の授業がALになるかどうかはわかりませんが、学生自身が書き込まないと資料が完成しないという意味では、学生の主体的な学びを引き出しているのではないかと思います。
【大西】フランスの学生の場合、授業の最後に課題を出してディスカッションします。概ね始めはフランス語で議論するのですが、教員が途中で質問しに行くなどの介入をすると、英語での議論に切り変わるようになります。始めは母国語で始めて、ある程度まで進んだら英語に切り替わるように刺激をするのもいいかと思います。ディスカッションの全てを英語で行うようにするのは、フランスの学生にとっても制約が大きくて、議論が進まない可能性もありますので、主体性を惹きだすにはそのような配慮も必要かと感じています。
【伊藤】大学院のグループ輪講(20分間)では、英語論文を読んでグループディスカッションを行いました。しかし、ディスカッションは日本語で行っています。日本語が母国語の学生しかいない中、ディスカッションまで英語にする必然性が薄かったのはあります。ALの要素に英語を用いるかどうかは、身につけてもらいたい内容などに応じて異なると感じています。
学生に対して、最終的に国際会議で英語討論ができるレベルに到達してもらいたい。就職後も海外エンジニアと英語でコミュニケーションできるレベルに到達してもらいたい。と考えると、英文を読むだけでは読解力しかつかないのではないか。スピーキングを磨きたいと考えたときにどうしたら良いと思うか。
【松村】国際会議で技術プレゼンテーションを行うことは、日常英語やビジネス英語よりも易しいと思います。私の場合、学生に英語プレゼンのテンプレートを先に渡しておきます。スライドのテンプレート、説明内容のテンプレート(導入部分や背景説明などの順序等)を伝えるのです。またどのような英語表現があるのかも、テンプレートとして渡しています。テンプレートの中に、自分の研究に関する言葉を入れていくだけで、5分くらいのプレゼンならできてしまう。後はそれを自分で覚えることで身についていきます。これを何度も繰り返して行きます。そのため技術プレゼンは一番やりやすいのではないかと思います。理系の学生は公式を憶えて、そこに数値を当てはめていくことはかなり得意なのではないでしょうか。英語も一緒で、公式さえあればそこに自分の言葉を書き込んでいくことは容易なのではないかと思います。はじめた当初はテンプレートを利用したとしても、うまくできることが学生の自信につながり、次に繋がっていくと思います。
質疑応答に関しても、ある程度テンプレートを与えておくと、パターンがわかるようになります。それを自分のものにしていくことで、段々と自分なりの討論ができるようになると思います。何も与えずに、全て学生に丸投げで「とにかくやってみて」は無理だと思います。
【大西】英語でも基本的なプレゼンパターンがあります。日本語をそのまま英語に訳すと、何が書いてあるのかわからない文章ができあがるので、英語の5文型で単語を並べなさいと指導しています。それでだいたいは伝わると思っています。ENSMMからの留学生も研究室にいますが、英語の5文型を並べるように指導しています。
【伊藤】英語プレゼン自体は事前に準備ができるので大丈夫だと思いますが、質疑応答の場面では英語力を問われます。特に専門用語があれば、理解できる部分もあると思いますが、ヒアリング力が必要になってくると思います。
英語力の極端に低い学生に対して、英語に対する恐怖心を取り除くにはどうしたら良いのか
【松村】私の授業の場合、授業は日本語で行っていますので、英語を理解していなくても授業の中身はわかります。いつか英語が必要になったときに、その専門用語の資料がありますよという気持ちでやっているので、英語が嫌いになってしまう学生はみたことがないです。私が教えている専門分野はグローバル生産技術ですから、生産技術の分野で活躍したいのであれば英語ができないとやっていけません。苦手かどうかではなく、英語で仕事が出来るようにならないと、就職後にとても困ることになると脅しています。英語は使いこなせないといけない。ただのツールであり、美しい英語を話す必要はありません。我々はネイティブではないので、技術を片言で話せるレベルで良いと思います。
【大西】ENSMMに連れていった日本人の学生は、帰国後、先方の学生が来日すると「英語で話したい」歓迎しようという姿勢が顕著に表れるようになります。ENSMMつながりで、共通の何かがあると思うのか、積極的に話かけるようになります。そういう意味では海外に学生を連れていくのは刺激としては一番良いのかと思います。自分が見たり興味があるものであれば、積極的に取り組めるであろうから、強制的にやらされるより、いい結果になります。興味を持ってもらえる機会を創ることが大切だと思います。
【伊藤】英語はツールだから重要だと強調しています。分からなくなったら聞きなさいと伝え、英語であなた達をテストしているわけじゃないということは、明確に伝えています。日本人学生が短期留学生と交流しているのを見ていると、英語が母国語ではない人が多い状況の方が気楽なようです。英語が母国語の人が多くて、その中で自分だけ英語ができないと萎縮してしまう。それぞれ英語が母語でない人が、お互い拙い英語で話し合う方が、全員でコミュニケーションを取ろうと頑張る気になるようです。
以上が本学教員による授業紹介です。各授業に共通していることは大切なことは「技術を理解してもらうこと」であり、英語力のレベル向上が目的ではないということです。「伝える手段」である英語をもっと身近に感じてもらえるよう、創意工夫した授業の事例紹介となりました。
- 大学紹介
- 基本情報
- 学長挨拶
- 顧問学長対談
- 副学長・学部長等 役職者
- 建学の精神と教育・研究理念
- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー
- 大学のあゆみ
- 大学の取り組み
- 情報公開
- 認証評価、自己点検・評価
- ホームカミングデー
- 東京電機大学が求める教員像
- 教育関係附置施設
- キャンパス紹介
- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー
- 学園紹介
- 学校法人東京電機大学概要
- 理事長挨拶
- 理事・監事
- 評議員
- 事業・財務情報
- ガバナンス
- 学園創立100周年宣言
- 学園広報物
- TDUコメンテーター教員紹介
- 学園へのご寄付
- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像
- 学園創立110周年記念事業
- 系列校・関連機関
- 寄附行為等
- 危機管理
- 新型コロナウイルス感染者状況
- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~
- 学部
- システムデザイン工学部
- 未来科学部
- 工学部
- 工学部第二部
- 理工学部
- 大学院
- 大学院での学び
- 先端科学技術研究科
- システムデザイン工学研究科
- 未来科学研究科
- 工学研究科
- 理工学研究科
- 入試・オープンキャンパス
- 大学入試
- 大学院入試
- インターネット出願/マイページ
- 入学者選抜要項
- 入試結果
- オープンキャンパス2025
- オンライン個別相談会
- 進学相談会
- キャンパス見学会
- キャンパス自由見学
- キャンパス見学
- メールマガジン
- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと
- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)
- 1分で電大が分かる!ショート動画
- 受験生への応援メッセージ
- キャリアプログラム
- 学内就職サイト
- 就職支援
- 資格取得・教員免許
- 公開講座
- 履修証明プログラム
- 実践知教育
- 留学・国際交流
- 本学へ留学希望の方
- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)
- 海外に留学希望の方
- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)
- 海外留学動画(学内者専用)
- 国際センター
- TDU International Workshop
- International Workshop
- スチューデントアンバサダー
- 国内でできる国際交流
- 在留期間更新許可申請
- 学生生活
- 学生要覧
- 履修の手引き
- 教職課程
- シラバス・時間割
- 年間予定
- 学習サポートセンター
- 学生アドバイザー
- 障害のある学生への支援
- その他授業関係
- 学費
- 奨学金
- 教育ローン・短期貸与金制度
- 保険制度・経費補助
- 証明書発行・事務窓口
- 学生相談室・健康相談室
- 休学・退学などについて
- クラブ・サークル活動
- 学生食堂と売店
- 車両通学
- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について
- 東京電機大学後援会
- 教育訓練給付制度